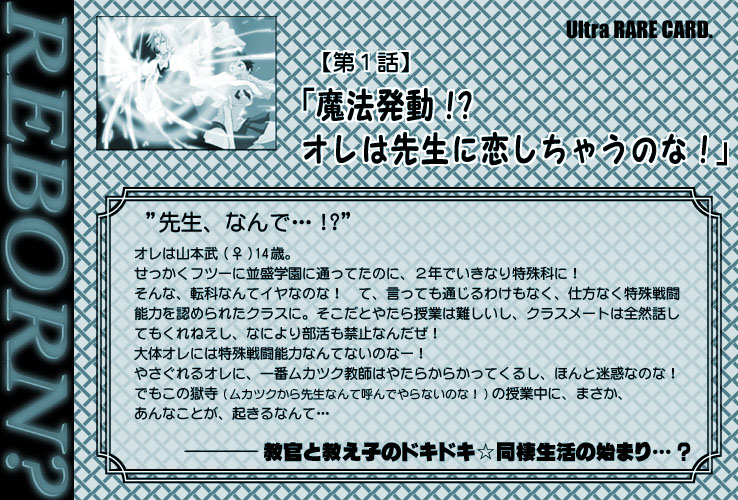★魔法学園★
いやこれなにって、
ニョタケシの妄想です。
(言い切った!)
※苦手な方は、これ以上進まないでね!※
元々は、
ロボがメッセンでニョタケシの
パラレルネタを語りだして。
まあ、それが通称「魔法学園」で。
冒頭は、こんな感じ。
・ニョタケシやツナたちは中学2年生。
・学校に通ってるけど、普通科と特殊(能力)科。
・元々普通科にいたけど、ニョタケシは素質を見出されて2年生から特殊科に。
・しかし部活は禁止で、エリート意識の強い特殊科に馴染めず。
・授業の脱走を繰り返していた頃に、臨時教官と出会う。
・いろいろあって、授業にも出始めたニョタケシ。
・けど、さっぱり分かんないのなー!
・つまらなそうにしてるニョタケシに、いろいろ構う臨時教官。
・実はこの教官、女生徒に人気が高いのでその意味でもやっかまれるニョタケシ。
・ニョタケシは全然気がついていないが、教官はなんとかしてやろうと策を弄す。
・授業中、ニョタケシを指名して実験に参加させる。
・見事に防いだニョタケシ!→クラスメートも絶賛、の予定。
・が、妬んでいたクラスメートの策略で、ニョタケシは防ぎきれない!
・危ない!となったところで、教官が自らかばう。
・ある意味、自業自得。
・が、助けてくれた教官に、キュン!しちゃうニョタケシ。
・でもあれだけ鬱陶しいと思ってたのに、キュンするのはおかしいと気づく。
・ハ!
・センセーがオレに恋の魔法かけたのなー!
・ずるいのな!
・ひどいのな!
・でも好き!(キュン!)
・いろいろあって、同居しました。
(早)
まあ、これ↑が冒頭で、
いろいろ続くって話だったんですが。
こんなネタを披露した翌日、
だっかな?
メッセンの相手(隠す意味はない)が、
うっかりしてました。
↓↓↓

獄寺先生ー!!!!!!!
(キュンキュン!)
ああ。
なんとなく分かってたと思いますが、
臨時教官は
ガッチ(=24獄)
です。
(バレてた!)
ちなみに↑は、
「獄寺センセに恋の魔法をかけられちゃったのな!」
の名シーン(?)です。
第1話。
(え)
みたいだなと思って、
ロボもうっかりしました。
↓↓↓
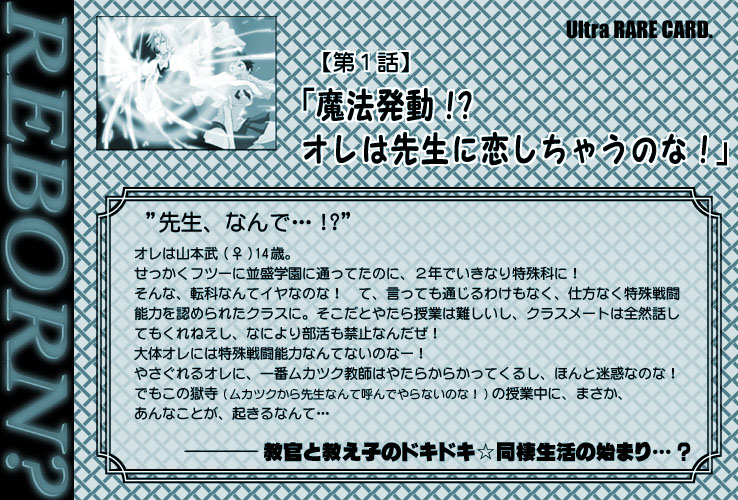
裏面作ってみました。
(どんなうっかりの仕方だyo!)
いや、
モティンコの画像が、
なんか特典カードとかみたいだなと思って(笑)
勝手に。
(待て)
ちなみに↑の元画像を使って、
もう一人うっかりしてたのがいたんですが、
なんかそっちは完成しないぽいので
放置プレイです。
(イヤなのなー!)
更に、
画像の追加弾☆
なんか、
EDテーマの映像みたいです。
(どこまでもアニメ仕様か!)
↓↓↓

パンチラー!!!!!
(それより胸)
で。
せっかくなので(?)、
ロボもちょっとうっかりしときました。
状況的には、
冒頭の説明から2ヶ月くらい後で、
同棲してるガチニョタです。
(断言!)
いろいろ不親切設計でスイマセンorz
本日は、土曜日。
珍しく養成所での実技指導もないので、久しぶりの連休だ。仕事ならばむしろ目覚ましの五分前には勝手に目が覚めるものだが、たまの休暇はそうもいかない。日頃自覚していない疲労がたまっているのか、それとも単に自分の性格が怠惰なのか。とにかく惰眠を貪ろうと決めたのは、きっと物心ついたときからだ。
つまり、そう簡単に直る性質ではない。
それにも関わらず、今朝もいつものように平日ならば始業前の時間帯に目が覚めてしまったのは、タイマー付の時計のような無機質な理由ではなかった。
「……あ!!」
「……。」
「獄寺のヤツ、まだ寝てる寝てるっ」
ギィ、と小さな音をさせて寝室の扉を勝手に開いてきたのは、二ヶ月ほど前から一緒に暮らしている相手だ。不本意ながらも、同居に至った経緯は今もって頭が痛い。だが決定事項として転がり込んできた教え子を無下にもできず、かといって当然教職員用の宿舎で匿い続けるわけにもいかず、結果的には『将来有望なので下宿させている』という苦しい言い訳で養成所近くの一軒家を借りることにした。
元々自分はここの臨時教官であるし、それほど後進の指導に熱心なわけでもない。教え子にしたところで、才能を見込まれて特殊科に転向したわりには実技以外の成績は低空飛行であるし、なにより遠方より通う生徒のための寄宿舎はちゃんと用意されているのだ。
「やっぱ起きてねえと思った。だって獄寺、休みだといっつも昼まで寝たがるしっ」
「……。」
「ほんっと、寝汚ねえのなっ。でもそんなトコもちょっと好……ん? いや、だらしねえんだし、キライだよな、うん。そーそー、キライなはずなのな、オレ」
お前がぶつぶつ言っているから起きてしまったと、文句の一つも言ってやりたい。いや、本当のところは、朝も早くから台所で一人ではしゃいでいた雰囲気がこの寝室まで流れてきて、寝ているはずでも無意識に気持ちをざわつかされて目が覚めてしまったのだ。
それをバカ正直に伝えるのは、どことなく悔しい。
十も年下の教え子に、なにをむきになっているのかと自己嫌悪することもある。だが調子に乗らせてはいけないのだと、もう心得ている。なにしろ、いまだに『魔法』にかかったつもりで、自分を嫌いになりたくて傍にいるようなバカなのだ。あまりに得意げにされると、ついからかいたくなって、嫌いにならせてやるという口実でこちらから何かをしでかしてしまいそうだ。
「……。」
「あれ、今獄寺起きた?……いや、やっぱ寝てるか」
自分を戒めるためにぐっと気を引き締めれば、そんなところばかり鋭い同居人は不思議そうに首を傾げている。だが結局寝ていると解釈したらしく、ペタペタと足音をさせてベッドに近づいてくる。その音がやたら床に吸い付いているようで、裸足なのだとぼんやりと思ったときには、すぐ近くまできていた足音はピタリと止まり、代わりにまだ少女らしい高めの声が降ってきていた。
「ごーくでらっ!! 朝なのな、起きてなのな!!」
「……。」
遠慮なくベッドを揺らしてくる同居人に、わずかばかりの抵抗で寝たふりを試みる。
どうせ、休みの日でもちゃんと早起きをすべきだとか、食事を抜いてはいけないだとか、どちらが年上か分からないようなことを言い出すに決まっている。結果的には起こされてしまうことは、この二ヶ月でもう諦めている。だがすぐに起きてやるのは唯々諾々として従っているようで癪だという微妙なプライドから、最初の一言では起きてやらないのだと決めていた。
「もうっ、獄寺、早く起きてほしいのな!! オレ、ずっと、困ってるのに……!!」
「……?」
「獄寺が起きてくれてたら、あんなことも……!!」
だがいつもならば次第に大きくなっていくはずの声も、ベッドを揺する手も、今朝は逆に小さくなっていった。しかも、何故か自分が責められているようだ。自分が朝起きていなかったばっかりに不幸に見舞われたとでも言いたげな声は、どことなく泣きそうにも聞こえ、痛ましい。こうして同居というかたちで引き取ることで、特殊科クラスでのおかしなやっかみなどからは守れてやっている気になっていたが、まさか、また何かあったのだろうか。
もしそうであれば、男として、いやそうではなく、教官として実に不甲斐ないと慌てて起きようとする前に、何故かタオルケットが引き剥がされていた。
「……。」
「なのに、獄寺、すやすや寝てて。ああもうっ、オレが眠くなってきたのも、全部、ぜーんぶ、獄寺の所為なのなー……。」
それは違うと思う。
そうと指摘もできないままに、同居人はするりとベッドに潜り込んできて、ちゃっかり横に収まってしまった。元々かなり体格差があるため、こうして同じベッドに寝転がることもさして苦ではない。
むしろ、心地よい。
いやそれは自分の盛大な勘違いであり、初夏の香り漂うこの時期に、この子供体温はむしろ暑苦しい。だが今はその体温すら微妙に感じられないと思ったときには、軽く身じろぎをした小さな教え子がしっかりと身を摺り寄せてきていた。
「……!?」
「ん、獄寺ぁ……。」
本気で眠くなっているのか、寝惚けたような甘ったるい声を出して、こちらの腕を枕にするように収まってくる。ちょうど胸の辺りに顔を埋め、擦りつけるようにして匂いを肺いっぱいに吸い込むと、安心したように大人しくなった。まるで動物のようだと微笑ましくなり、つい撫でたくなって手を伸ばしかける。それに、起きていることがバレてしまうと慌てて止めかけたが、こうして二人で寝る方が余計に問題だと思い直してなんとかその手を肩に置いた。
「……ん?」
「おい、バカ、起きろ。なに寝てんだよ……。」
「んー……あ、獄寺?」
どうやらこの一瞬で、本当に意識が落ちかけていたらしい。すっかりとろけていた目を向けた同居人、教え子であるはずの山本武は、しばらくぼんやりとこちらを見つめた後、急に拗ねていた。
「……獄寺、ひでえのなっ」
「だから、何がだよ……?」
一瞬、これでは起きたばかりだという設定ではおかしな言い回しだと焦ったが、幸いにして山本は気がついていない。そういう鈍さにはほっとしたところで、いきなりハッと息を飲んだ山本は、両腕を首に回すようにして抱きついてくる。
「うぐっ……!?」
「忘れてたのなっ、起きたらまずはオハヨーの挨拶なのな!!」
「あ、ああ……!!」
「獄寺、おはよう、おはよーう!!」
躾がいいのか、できていないのか。
非常に悩むところである。確かに朝にちゃんと挨拶をしようとするのは礼儀正しいだろうが、それを、男のベッドに潜り込んであまつさえギュウギュウと抱きついてまでするのか、どうなのか。実年齢にはるかに達していないと思われる精神年齢とは対照的に、山本の体は女性として非常に恵まれて豊満だ。心が幼すぎて自覚がないならまだしも、山本は魔法だ何だと言いがかりはつけつつ、ちゃんと自分に恋をしているのだ。それでいてこの態度は、本気で性欲というものに対する意識が欠如しているのか、あるいはそうなっても構わないという慎ましやかな意思表示だろう。
要するに、誘っている。
そんな都合のいい推測に自分が至ってしまう前に、そろそろ気道を潰してくれそうな勢いの腕をなんとか外させることにしていた。
「バ、バカッ、苦しいだろうが……!!」
「あ、わりぃ」
咳き込みつつ腕をぐっとつかめば、ようやく制裁的な力は緩められる。それでもまだ細い両腕は首から背中に回されたままで、こちらが体を起こしても同じようにして外すつもりはない様子だ。
「でも、獄寺、おはよーなのな」
「分かったっての、それは。だから、それより、オレが悪いとかってのは……。」
「おはよーなのな」
「それはもう聞いたって言っただろ? オレもちゃんと起きたし、だから……。」
「おはよー」
「だから山本……。」
「おはよー」
「山本……?」
「おはよー、なのな!!」
「……。」
「……うー」
「バカ、唸るな。分かった分かった、おはよう、だな?」
「ん、おはよー!!」
どうやら、こちらにも言わせたかっただけらしい。仕方なく、普段は、いやこの山本と同居するまでは稀にお会いする十代目にしかしなかったような朝の挨拶を口にする。
すると、山本は本当に嬉しそうに笑うのだ。
へらっとしまりない笑みを浮かべ、再びオハヨウオハヨウとそれしか言葉を知らない鳥のように繰り返している。その間もまた腕に力が込められ始めたので、どうやら離す気はないらしいと察して仕方なく腰を引き寄せた。
「ん?」
「……だから、オレが起きてなかったことで、何があったんだよ」
そのまま山本を首からぶら下げるようにして、ベッドから降りる。身長差があるので床に足がつかない山本は、腕を緩めて下りるのではなく、逆にしっかりとしがみついてきていた。さほど体重もないし、山本の方からも姿勢を整えてくれれば片腕を腰の後ろに回しているだけでも、充分に支えられる。それ自体は問題はないものの、むぎゅっと押し付けられる胸には、予想していたとはいえ軽く舌打ちしてしまう。
「……ったく、てめーは」
「んー? あっ、だって苦しいから仕方ないのな!! 家の中だから、ブラしてなくてもいいのな!!」
「んなこと言ってたら、形崩れっぞ……。」
これだけ豊満なんだし、と思いつつ、言葉には出せないのは意識してしまいそうだからだ。常々、山本は挨拶をしろだの食事はちゃんと取れだのと、山本のルールを押し付けてくる。だがこちらから提示したものは、なかなか守ってもらえないのだ。二人で円満に生活していくために、というより、むしろ山本に身の安全を思っての親切であるのに、一向に聞き入れてくれる様子がないのはやはり誘っているのか。
そんな思考にまた至りかけるが、このとき山本は珍しく聞き返してきていた。
「……オレのおっぱいのカタチ崩れたら、獄寺、イヤ?」
「あ、ああ……? というか、お前が自分で嫌なんじゃ……?」
「んー、それならしよっかな……あ。いや、えっと、獄寺がイヤなら、その方がいいんだし? あれ? いやオレが獄寺をイヤになりてえんだから、えっと、このまま口うるさく言われた方がいいのかな? でも言ってくれるの、別にイヤじゃねえし、むしろオレのこと心配してくれてるみたいでちょっと嬉しいし、じゃあやっぱり……?」
「……バカ、もういい。バカなんだから混乱するだけだろ」
ただでさえ容量が少ない脳みそを朝から酷使してやるなと撫でてやれば、嬉しそうに怒るという器用なことを山本はしてみせていた。だがいつまでもこの調子に構っていれば日が暮れることはもう自明だったので、欠伸をかみ殺しながら取り敢えずは寝室から出る。
「あ、獄寺、台所!!」
「……そういやメシ作ってたのか?」
「ん!!」
特に希望がなければ、顔を洗うために洗面所に向かおうとかと思ったのだが、抱えたままの山本に指示されてしまった。仕方なく廊下の反対側へ進み、ダイニングキッチンへと出れば、そこにはいかにも途中といった様子で食事作りが放置されていた。
「……。」
「獄寺が、和食ばっかりもイヤだって言うから。せっかく洋食にしてたのに、コショウが空だったのな!!」
「……そら悪かったな」
実家が寿司屋のためか、山本はこの年にしては充分すぎるほどの料理の腕は持っている。家事に関してはやはり手伝い程度だったようだが、一通りはできるのでここに来てからもう充分にこなせていた。学校で好意的にこの同居を見てくれる者からは、山本を家政婦代わりに使っているのだと言われるほど、山本は家政婦としてならば有能だ。だが大半の者からすれば山本の家事の器用さも、単なる花嫁修行の成果にしか見えないようで、からかわれる一因にもなっていた。
そんな山本だが、唯一食事に関して不満というか、偏りがあるとすればそのメニューだ。実家が和食中心なためか、いわゆる和食か、家庭料理のようなものしかレパートリーがないのである。それなりに和食も好んでいるが、やはり自分は半分以上の血が本国イタリアのものなので、そればかりだとどこか物足りない。面と向かって言った記憶はないが、山本はそのあたりを感じ取ってくれていたようだ。作りかけの様子と、開かれた家庭科の教科書から察するに、目玉焼きとトーストだけのようだが、それでも少し面映い気持ちになった。それがお前の思うところの洋食なのかだとか、和食のときと種類も手の込みようも落差がありすぎるだとか、そんなことは関係ない。その気持ちだけで嬉しいのだ、と返したいところだが、生憎目玉焼きはまだ完成していなかった。
「けどよ、調味料のストックはあるはずだろ? 山本も一緒に買ったじゃねえか」
二ヶ月ほど前、この家に引っ越すと決まった際に、荷造りを手伝っていた山本が突然暴れだしたのだ。いや、単に興奮して問い質してきたのだが、胸倉をつかまれてガクガクと揺さぶられたので、何事かと焦った。そうまでして山本が慌てふためいて叫んだのは、甚だ不可解なことだった。
『ご、獄寺って、もしかして本当に魔法使いなのな!?』
『ハ……!?』
だいぶ意味が分からなかったものの、根気よく尋ねてみれば、どうやら食器や料理道具、調味料など、食事に関するものがほとんどなかったことが不思議だったらしい。理由は単純に、教官用の宿舎で暮らしていた獄寺は、基本的に外食だっただけだ。部屋で自炊などするはずもなく、たまに持ち込んで食べる際にかける程度で塩やコショウがあったくらいだ。
だが山本はそうは思わなかったようで、食事を作らない、つまり食べていない、霞でも食っているのかと慌てたらしい。その思考回路の方がよほど浮世離れしていると思いつつ、山本にせがまれて必要と言われたものは一式揃えてやったはずだった。
「それは覚えてるのなっ」
「だったら、新しいの出せばいいだろ?」
コショウに関しては、以前の宿舎から使っていた数少ない調味料の一つだ。そのため、ちょうど切れてしまったらしい。だがストックはあったはずだと指摘すれば、ますます山本は拗ねてしまったようだ。
「……だって、獄寺が」
「しまった場所、忘れたのか? ほら、そこのシンクの上の収納の……?」
「だからそれも分かってるのなっ、なのに獄寺が意地悪すっから!!」
新しいコショウが置いてある場所も分かっているのに、どうして自分は怒られているのか。さっぱり分からないとばかりにコショウが鎮座しているはずの収納扉を見上げれば、その角度にようやく分かった気がした。
「獄寺がっ……オレの、手が届かないトコに置いたりすっから」
「あー、そういや、オレでもギリギリだったな……。」
この家は獄寺が一人で下見をしてすぐに決めてしまったので、山本の意見は取り入れられていない。そのため、基本的には水周りが充実していないのだ。あまり広くない台所で山本はそれでもせっせと作ってくれているが、収納に関しては狭すぎてスペースをかなり上方にしか取れなかったらしい。もちろんシンク前に立って山本でも余裕で手が届くところにもあるが、そこには普段からよく使う鍋類などが仕舞われている。たまにしか出さない調味料の予備など置いておく余裕はなく、扉そのものは一枚になっていても、中が三段に仕切られた一番上に新しいコショウなどは置いたはずだった。
「バカ、てめーそんなことで拗ねてたのかよ」
だが分かってしまった不機嫌の理由に、どこか安堵もしていればつい呆れたような言い回しになってしまう。すると山本はますます頬を膨らませ、しがみついている手で髪を引っ張ってくる。
「だって、獄寺がイジワルだから……!!」
「そんなつもりじゃなかったけどよ、でもまあ、椅子でも使えばよかっただろ?」
「!?」
確かにそのままでは手が届かないだろうが、何か足場になるものを持ってくればよかったはずだ。振り返ればすぐにダイニングテーブルに備え付けられた椅子があるので、引き摺ってくるのも容易い。そうすれば簡単に取れただろうと指摘すれば、ハッと息を飲んだ山本は、更にギュウギュウと髪を引っ張ってきていた。
「そ、それぐらいっ、オレだって分かってたのな!! ほんとなのな!! でも、獄寺がイジワルだっての、言わなきゃと思って……!!」
「痛ててててっ、バカ、そんな引っ張んな!? あーもうっ、分かった分かった、オレが悪かったことにしてやっから、な……!!」
年頃の小娘は本当に扱いづらいと嘆きつつ、こうして懐かれるのも悪くないと思ってしまうのがなんだか億劫だ。そうしている間に、おざなりすぎる謝罪でも機嫌を直したらしい山本は、あっさり髪をつかむ手は離して口を開いていた。
「じゃあ、コショウ取って?」
ほら、と収納扉は山本が開けてくれるが、やはり一番上の棚は高い。確か仕舞うときも、獄寺ですら手元が見えないままに適当に押し込んだ記憶があるのだ。下からではどこにコショウがあるのかよく分からないとため息をつき、獄寺は空いていた手を山本の太腿の下辺りに回す。
「ん?」
「持ち上げてやっから、テメェが取れよ」
そうして腕に座らせるようにして持ち上げ、向きも反転させれば山本は器用に肩に乗ってきた。そうすればさすがに視点も高く、ちゃんとラベルまで拝むことができたらしい山本は嬉しそうに棚へと手を伸ばしていた。
「あった、あった」
「バカッ、喜ぶのはいいから足ばたつかせてんじゃねえ……!!」
だが無邪気に足をバタバタされると、ちょうど踵が腹の横に当たって蹴られるのだ。痛いと文句を言えばピタリと止まるが、どうやら山本は聞いていないらしい。
「じゃあ獄寺、すぐにゴハンの支度するのな!!」
「……ああ」
「顔洗って、着替えてきたらちょうどいいくらい? ほら、早く行っ……て、オレも連れてっちゃダメなのなー!!」
名残惜しい体温を床へとおろせば、山本はもう獄寺から興味をなくしたように新しいコショウのパッケージをはがしている。それになんとなくため息をつこうとすればかみ殺し忘れた欠伸が出たが、耳ざとく聞かれてしまったらしい。
「あ、獄寺。今日は二度寝はダメだからなっ、天気いいからシーツとかも干すし!!」
「……分かった」
内心舌打ちをしてしまったのは、まさに朝食だけ平らげてまた寝ようと思っていたからである。先に釘を刺されてまた面白くなくなっていると、山本は新しいコショウを試し振りして派手にクシャミをしながら、続けていた。
「へくしっ……だ、だから、寝るときは居間のカウチで寝てほしいのなっ」
「……ああ」
「オレも洗濯終わったら寝るし」
意外にも、二度寝自体は禁止されなかったらしい。そのことに少しほっとするが、続けられた言葉には完全に足を止めて不思議そうに聞き返してしまった。
「けど、カウチは一つしかねえだろ?」
「ん? でも獄寺の上はあいてるだろ?」
「……。」
どうやら、また一緒に寝るつもりらしい。そのことにため息をついたのは、乗られる重さに対してではなく、相変わらずな格好で懐かれると今度こそいろいろまずそうだという自覚からだ。
山本は、恋をしている。
そのことは認めていても、恋していることはイヤなのだ。
腹立たしいからと手を出せば、それこそ山本が望むとおり、この恋は終わってしまうかもしれない。性的なことには全く知識も意識も追いつかない山本にはまだ何もできるはずがなく、こうしてため息を深めてしまうということは、結局こんな生活を長続きさせたいと自分も思っているのか。
「……ガキ相手に、なにマジになってんだか」
「んー? 獄寺、なんか言った?」
十も年下の、少女と言って差し支えないしかも教え子に、振り回されている自覚はある。ささやかな仕返しくらいはいいだろうと思い、どうやら二度寝するつもりらしい山本に笑いながら答えておいた。
「ああ、二度寝はしねえよ、て言ったんだ。そろそろまた足りねえものとか出てきてるだろ、洗濯終わったら買い出しに行くぞ」
自分一人で外出をしても、山本が家で悠々とカウチで惰眠を貪るだけだ。そうはさせないと、連れ出すつもりだと言ってみれば、何故か山本はポカンとしている。確かに唐突な予定だっただろうが、そこまで驚くことだろうか。もしかして山本には何か予定でもあったのかと勘繰る前に、急に顔を真っ赤にした山本が怒り出していた。
「そ、そんなっ、デートとかでオレ喜ばせるのずるいのな!! オレは獄寺を嫌いになりたくているのにっ、朝から、こんな、ずっと嬉しいことばっかりしちゃやーなのな!!」
「……じゃあ行くのやめるか?」
「それはもっとやーなのな!!」
本当に獄寺を嫌いになりたいのであれば、買い出しに行きたい山本に応じない方がいいはずで、この場合山本は行かなくていいという答えになるはずだ。だが山本は、やはりどこまでも自分の欲求に忠実だ。
時に面倒で、不可解で、複雑な思いがすることになる。それでも、あのとき『魔法』などかけていないと知っている自分には、どうあっても面映いだけだ。
「分かった分かった、行ってやるから安心しろ」
「絶対なのな、嘘ついちゃダメなのなー!!」
ハイハイと適当に頷いてやり、今度こそ洗面所に向かえば台所から鼻歌も聞こえてくる。ごくでらとでーとうれしいなー、などと外れた調子で歌われているのが耳に入れば、もう仕方がないと認めるしかない。
あのバカは、これが恋ではない。
だがきっと自分は、あんなバカにとっくに恋してしまっているのだろう、と。
|
大体、こんな感じ。
一番のアレ具合は、
ほんとにこんな本を出そうと思ってたことです。
(うっかりー!!!!!)
妄想に付き合ってくれたモティンコ、
本当にありがとうハァハァ!!!
というか、
ほんとにガチニョタ好きなんだね
と
痛感した逸話でした。
(あたしも好きだけどもー!!)